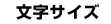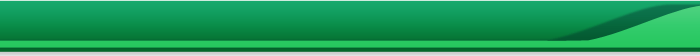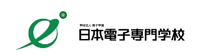日本電子専門学校同窓会 > とくとくコーナー
とくとくコーナー クイズに答えて素敵な賞品をもらおう!
2010年07月
問題:夏の風物詩「花火」に関するうんちくクイズ
次の記述のうち間違っているものはどれでしょう。
1. 日本で最も古い花火大会は「隅田川花火大会」で「両国の川開き」と呼んでいた。
2. ギネス認定の世界最大の花火は4尺玉で、打ち上げ時に直径800mにも広がる。
3. 花火のルーツは中国だが、観賞用の花火はイタリアが最初である。
4. 「たまや〜」「かぎや〜」というかけ声は、江戸時代の花火業者に由来している。
5. 日本で最初に花火を見たのは豊臣秀吉だと言われている。
1. 日本で最も古い花火大会は「隅田川花火大会」で「両国の川開き」と呼んでいた。
2. ギネス認定の世界最大の花火は4尺玉で、打ち上げ時に直径800mにも広がる。
3. 花火のルーツは中国だが、観賞用の花火はイタリアが最初である。
4. 「たまや〜」「かぎや〜」というかけ声は、江戸時代の花火業者に由来している。
5. 日本で最初に花火を見たのは豊臣秀吉だと言われている。
■賞品:東京ディズニーランド 1dayパスポートペアチケット 1組
■回答:番号でお答えください
■締め切り:2010年08月31日 (火)
■発表:メールマガジン2010年09月25日号にて。
※受付期間を過ぎたもの、必要事項がすべて記入されていないものは無効となります。
※とくとくコーナーはメールマガジン会員様のプレゼント企画です。
ご応募にはメールマガジン会員様に配布されるアクセスキーが必要ですのでご注意下さい。
メールマガジン会員新規登録はコチラ>>
クイズの答え
解答:5
解説:
1. 日本で最も古い花火大会は「隅田川花火大会」で「両国の川開き」と呼んでいた。
歴史に残る最古の花火大会は、享保18年(1733年)、8代将軍徳川吉宗が、前年の大飢饉と疫病で亡くなった人々の慰霊のために隅田川で水神祭を行ったとき、両国橋周辺の料理屋が花火を打ち上げたのが最初と言われている。「隅田川花火大会」という名称は昭和53年から採用された新しい名称で、それ以前は「両国の川開き」と呼ばれていた。
2. ギネス認定の世界最大の花火は4尺玉で、打ち上げ時に直径800mにも広がる。
世界一巨大な花火は四尺玉、つまり直径1.2mほどもあり、ギネス認定となっている。この四尺玉の重さは420kg。これを打ち上げると、直径800mもの大輪を咲かせる。この迫力満点の四尺玉を見ることができるのは、新潟県片貝で開催される「片貝まつり」でのみ。片貝は三尺玉発祥の地として400年もの歴史を持ち、昭和60年に初めて四尺玉の打ち上げに成功した。
3. 花火のルーツは中国だが、観賞用の花火はイタリアが最初である。
花火のルーツは、紀元前3世紀、中国で「硝石」から火薬が発明され、秦の始皇帝時代に万里の長城で“のろし”として使われたのが最初だと言われている。
観賞用の花火は、14世紀にイタリアのフィレンツェで作られたという説が有力。当時はキリスト教の祝祭などで、見世物として使われたようで、一説によると、「火を噴く人形」のようなものだったと言われている。以降、花火はヨーロッパ全土に広がっていき、貴族の権力を誇示するために王が催すイベントなどで打ち上げられるようになっていった。
4. 「たまや〜」「かぎや〜」というかけ声は、江戸時代の花火業者に由来している。
実在した「玉屋」と「鍵屋」という人気花火師に由来している。当時の花火大会は両者の二大競演で、観客たちは応援の意味を込めて「たまや~!」「かぎや~!」と掛け合い、花火を楽しんだ。現在、「鍵屋」は東京で「宗家花火鍵屋」として受け継がれ、「玉屋」は千葉で「元祖玉屋」として残っている。
5.日本で最初に花火を観たのは、徳川家康だと言われている。
『駿府政事録』によると「慶長18年(1613年)、駿府城でイギリス人が徳川家康に花火を披露した」とあり、日本で最初に花火を観たのは徳川家康だと言われている。このイギリス人は、時のイギリス国王ジェームズ一世の使者であるジョン・セーリスという人物。このとき、家康に渡された親書の現物が大英博物館に保管されている。
解説:
1. 日本で最も古い花火大会は「隅田川花火大会」で「両国の川開き」と呼んでいた。
歴史に残る最古の花火大会は、享保18年(1733年)、8代将軍徳川吉宗が、前年の大飢饉と疫病で亡くなった人々の慰霊のために隅田川で水神祭を行ったとき、両国橋周辺の料理屋が花火を打ち上げたのが最初と言われている。「隅田川花火大会」という名称は昭和53年から採用された新しい名称で、それ以前は「両国の川開き」と呼ばれていた。
2. ギネス認定の世界最大の花火は4尺玉で、打ち上げ時に直径800mにも広がる。
世界一巨大な花火は四尺玉、つまり直径1.2mほどもあり、ギネス認定となっている。この四尺玉の重さは420kg。これを打ち上げると、直径800mもの大輪を咲かせる。この迫力満点の四尺玉を見ることができるのは、新潟県片貝で開催される「片貝まつり」でのみ。片貝は三尺玉発祥の地として400年もの歴史を持ち、昭和60年に初めて四尺玉の打ち上げに成功した。
3. 花火のルーツは中国だが、観賞用の花火はイタリアが最初である。
花火のルーツは、紀元前3世紀、中国で「硝石」から火薬が発明され、秦の始皇帝時代に万里の長城で“のろし”として使われたのが最初だと言われている。
観賞用の花火は、14世紀にイタリアのフィレンツェで作られたという説が有力。当時はキリスト教の祝祭などで、見世物として使われたようで、一説によると、「火を噴く人形」のようなものだったと言われている。以降、花火はヨーロッパ全土に広がっていき、貴族の権力を誇示するために王が催すイベントなどで打ち上げられるようになっていった。
4. 「たまや〜」「かぎや〜」というかけ声は、江戸時代の花火業者に由来している。
実在した「玉屋」と「鍵屋」という人気花火師に由来している。当時の花火大会は両者の二大競演で、観客たちは応援の意味を込めて「たまや~!」「かぎや~!」と掛け合い、花火を楽しんだ。現在、「鍵屋」は東京で「宗家花火鍵屋」として受け継がれ、「玉屋」は千葉で「元祖玉屋」として残っている。
5.日本で最初に花火を観たのは、徳川家康だと言われている。
『駿府政事録』によると「慶長18年(1613年)、駿府城でイギリス人が徳川家康に花火を披露した」とあり、日本で最初に花火を観たのは徳川家康だと言われている。このイギリス人は、時のイギリス国王ジェームズ一世の使者であるジョン・セーリスという人物。このとき、家康に渡された親書の現物が大英博物館に保管されている。
【 当選発表 】
S・Kさん(情報ビジネス科 2007卒業)
現在応募期間対象外です。 S・Kさん(情報ビジネス科 2007卒業)
- 次へ>>

- 146

- 145

- 144

- 143

- 142

- 141

- 140

- 139

- 138

- 137

- 136

- 135

- 134

- 133

- 132

- 131

- 130

- 129

- 128

- 127

- 126

- 125

- 124

- 123

- 122

- 121

- 120

- 119

- 118

- 117

- 116

- 115

- 114

- 113

- 112

- 111

- 110

- 109

- 108

- 107

- 106

- 105

- 104

- 103

- 102

- 101

- 100

- 99

- 98

- 97

- 96

- 95

- 94

- 93

- 92

- 91

- 90

- 89

- 88

- 87

- 86

- 85

- 84

- 83

- 82

- 81

- 80

- 79

- 78

- 77

- 76

- 75

- 74

- 73

- 72

- 71

- 70

- 69

- 68

- 67

- 66

- 65

- 64

- 63

- 62

- 61

- 60

- 59

- 58

- 57

- 56

- 55

- 54

- 53

- 52

- 51

- 50

- 49

- 48

- 47

- 46

- 45

- 44

- 43

- 42

- 41

- 40

- 39

- 38

- 37

- 36

- 35

- 34

- 33

- 32

- 31

- 30

- 29

- 28

- 27

- 26

- 25

- 24

- 23

- 22

- 21

- 20

- 19

- 18

- 17

- 16

- 15

- 14

- 13

- 12

- 11

- 10

- 9

- 8

- 7

- 6

- 5

- 4

- 3

- 2

- 1

- <<前へ