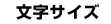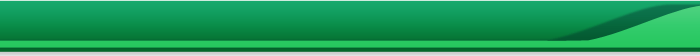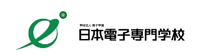日本電子専門学校同窓会 > とくとくコーナー
とくとくコーナー クイズに答えて素敵な賞品をもらおう!
2011年05月
サクランボ(桜桃)にちなんだうんちくクイズ!!
うっとうしい梅雨の季節がはじまります。そんな季節でも、ちょっと気分を爽やかにしてくれるのが、甘酸っぱいサクランボ。今回は、6月の旬の果物・サクランボにちなんだうんちくクイズです。
問題:サクランボ(桜桃)にちなんだ次の記述のうち、間違っているものはどれでしょうか。
1. ソメイヨシノなどの観賞用の桜の木からは、いわゆる食用サクランボはできない
2. サクランボの王様と言われる「佐藤錦」の生みの親は、佐藤さんである
3. 「佐藤錦」は、当初「マリー・アントワネット」という名だった
4. 6月19日は太宰治を偲ぶ「桜桃忌」で、太宰治が自殺した日である
5. 日本のサクランボの約7割は山形県で収穫される
問題:サクランボ(桜桃)にちなんだ次の記述のうち、間違っているものはどれでしょうか。
1. ソメイヨシノなどの観賞用の桜の木からは、いわゆる食用サクランボはできない
2. サクランボの王様と言われる「佐藤錦」の生みの親は、佐藤さんである
3. 「佐藤錦」は、当初「マリー・アントワネット」という名だった
4. 6月19日は太宰治を偲ぶ「桜桃忌」で、太宰治が自殺した日である
5. 日本のサクランボの約7割は山形県で収穫される
■賞品:東京ディズニーランド 1dayパスポートペアチケット 1組
■回答:番号でお答えください
■締め切り:2011年06月10日 (金)
■発表:メールマガジン2011年06月27日号にて。
※受付期間を過ぎたもの、必要事項がすべて記入されていないものは無効となります。
※とくとくコーナーはメールマガジン会員様のプレゼント企画です。
ご応募にはメールマガジン会員様に配布されるアクセスキーが必要ですのでご注意下さい。
メールマガジン会員新規登録はコチラ>>
クイズの答え
■ 正解:4
“さくらんぼ”にちなんだうんちく
1. ソメイヨシノなどの観賞用の桜の木からは、いわゆる食用サクランボはできない
観賞用の桜の木でも実はなるが、小さいだけでなく、酸っぱくて食用にはならない。いわゆるサクランボは、セイヨウミザクラ(西洋実桜)という全く別の種類の桜の実である。
2. 3.サクランボの王様と言われる「佐藤錦」の生みの親は、佐藤さんで、当初は「マリーアントワネット」と命名した
佐藤錦は山形県の農家、佐藤栄助氏が、「ナポレオン」と「黄玉」という2種類のサクランボを交配させて育成した品種。当初は、フランスの皇帝にちなんだ「ナポレオン」から生まれた新種という意味と、サクランボの女王という意味も込めて、同じくフランスの王女である「マリーアントワネット」と命名したが、時は、昭和初期の国粋期。横文字がだめなら、いっそ自分の名前ということで「佐藤錦」と命名した。
4.太宰治を偲ぶ「桜桃忌」は、太宰の誕生日である
1948年6月13日、太宰治は愛人・山崎富栄とともに玉川上水(東京都三鷹市付近)に入水自殺した。没年38歳。だが、遺体が上がったのは6日後の6月19日。くしくもこの日は、太宰の誕生日でもあったことから、太宰を偲ぶ日となった。「桜桃忌」の名付け親は、同郷で太宰と親交の深かった直木賞作家・今官一である。太宰晩年の短編小説「桜桃」の名にちなんで命名した。
5.日本のサクランボの約7割は山形県で収穫される
日本のサクランボの収穫は、約7割が山形県から。残りが青森、山梨、北海道である。
“さくらんぼ”にちなんだうんちく
1. ソメイヨシノなどの観賞用の桜の木からは、いわゆる食用サクランボはできない
観賞用の桜の木でも実はなるが、小さいだけでなく、酸っぱくて食用にはならない。いわゆるサクランボは、セイヨウミザクラ(西洋実桜)という全く別の種類の桜の実である。
2. 3.サクランボの王様と言われる「佐藤錦」の生みの親は、佐藤さんで、当初は「マリーアントワネット」と命名した
佐藤錦は山形県の農家、佐藤栄助氏が、「ナポレオン」と「黄玉」という2種類のサクランボを交配させて育成した品種。当初は、フランスの皇帝にちなんだ「ナポレオン」から生まれた新種という意味と、サクランボの女王という意味も込めて、同じくフランスの王女である「マリーアントワネット」と命名したが、時は、昭和初期の国粋期。横文字がだめなら、いっそ自分の名前ということで「佐藤錦」と命名した。
4.太宰治を偲ぶ「桜桃忌」は、太宰の誕生日である
1948年6月13日、太宰治は愛人・山崎富栄とともに玉川上水(東京都三鷹市付近)に入水自殺した。没年38歳。だが、遺体が上がったのは6日後の6月19日。くしくもこの日は、太宰の誕生日でもあったことから、太宰を偲ぶ日となった。「桜桃忌」の名付け親は、同郷で太宰と親交の深かった直木賞作家・今官一である。太宰晩年の短編小説「桜桃」の名にちなんで命名した。
5.日本のサクランボの約7割は山形県で収穫される
日本のサクランボの収穫は、約7割が山形県から。残りが青森、山梨、北海道である。
【 当選発表 】
E.Tさん コンピュータ・アミューズメント科 1997年卒
現在応募期間対象外です。 E.Tさん コンピュータ・アミューズメント科 1997年卒
- 次へ>>

- 147

- 146

- 145

- 144

- 143

- 142

- 141

- 140

- 139

- 138

- 137

- 136

- 135

- 134

- 133

- 132

- 131

- 130

- 129

- 128

- 127

- 126

- 125

- 124

- 123

- 122

- 121

- 120

- 119

- 118

- 117

- 116

- 115

- 114

- 113

- 112

- 111

- 110

- 109

- 108

- 107

- 106

- 105

- 104

- 103

- 102

- 101

- 100

- 99

- 98

- 97

- 96

- 95

- 94

- 93

- 92

- 91

- 90

- 89

- 88

- 87

- 86

- 85

- 84

- 83

- 82

- 81

- 80

- 79

- 78

- 77

- 76

- 75

- 74

- 73

- 72

- 71

- 70

- 69

- 68

- 67

- 66

- 65

- 64

- 63

- 62

- 61

- 60

- 59

- 58

- 57

- 56

- 55

- 54

- 53

- 52

- 51

- 50

- 49

- 48

- 47

- 46

- 45

- 44

- 43

- 42

- 41

- 40

- 39

- 38

- 37

- 36

- 35

- 34

- 33

- 32

- 31

- 30

- 29

- 28

- 27

- 26

- 25

- 24

- 23

- 22

- 21

- 20

- 19

- 18

- 17

- 16

- 15

- 14

- 13

- 12

- 11

- 10

- 9

- 8

- 7

- 6

- 5

- 4

- 3

- 2

- 1

- <<前へ